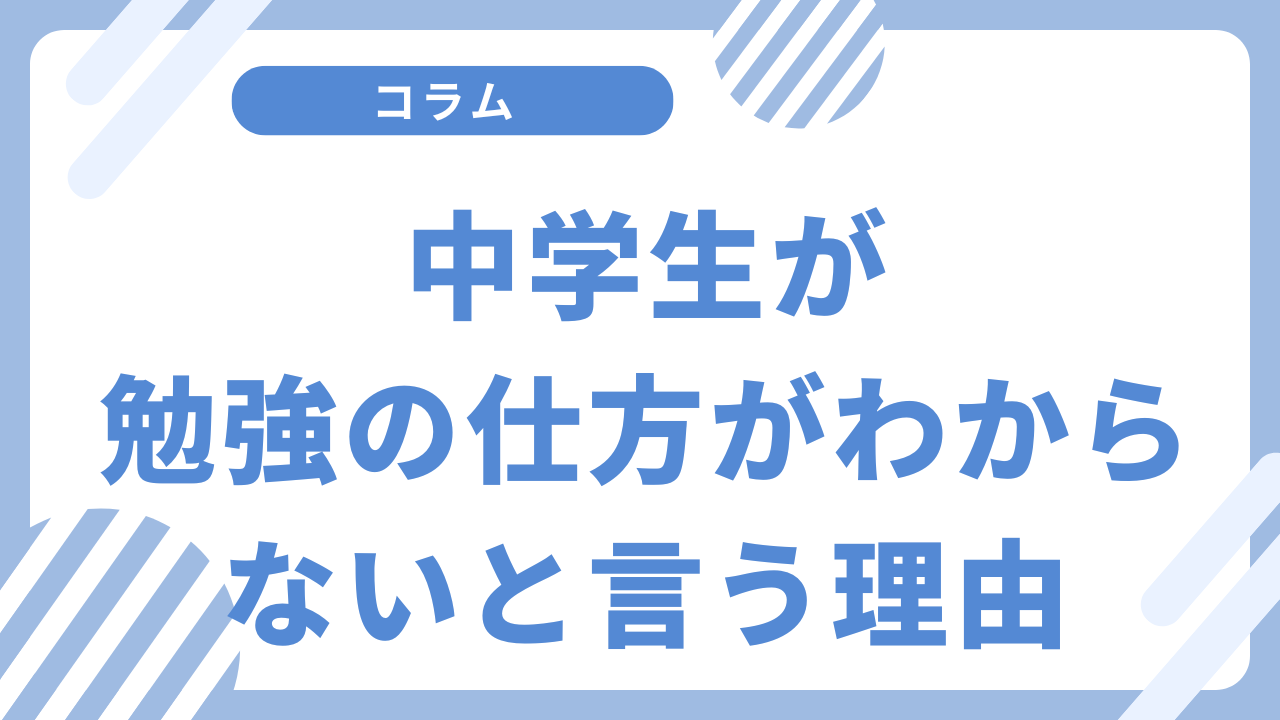
中学生の勉強の仕方が分からない!その原因とおすすめの勉強法を徹底解説!

勉強の仕方がわからなくて、中学の勉強についていけない。そんなときは、現在の学力を把握し、自分にあった勉強法を見つけることが大事です。勉強のモチベーション維持のためには、勉強の目的を見つけ、計画立てて勉強することが必要となります。
勉強の習慣をつけるためには、自宅学習に慣れるようにしましょう。親は子どものサポートをし、栄養や睡眠に気を使って勉強のための体調を整えるようにしてあげてください。
\ LINE限定プレゼント /
【中学生必見】勉強の仕方が分からない4つの原因

勉強の仕方が分からない原因には、いくつかの共通点があります。
まず、学習計画の立て方や進め方が分からないことです。
次に、目標や目的が曖昧なことが挙げられます。何のために勉強するのかが明確でないと、勉強へのモチベーションが上がりません。また、苦手分野を放置しているせいで、先の内容が身についていない場合もあります。
①勉強の仕方を教えてもらっていないから
中学生の多くが「勉強の仕方が分からない」と感じる背景には、「勉強の仕方」を具体的に教えてもらった経験がないことが挙げられます。学校では、教科ごとの知識や解法は教えられるものの、どのように効率よく学習を進めるかについて詳しく教わる機会は少ないのが現状です。その結果、ただ漠然と教科書や問題集を読むだけになり、成果が出ないまま挫折してしまうことがあります。
また、「勉強の仕方」は一人ひとり異なり、自分に合った方法を見つけるには試行錯誤が必要です。しかし、多くの中学生はその方法を知らず、他人のやり方を真似するだけで自分に適しているかを考えられないことが多いです。
この問題を解決するには、まずは「具体的な勉強方法」を学ぶことが重要となります。例えば、目標を設定して計画を立てることや、復習を習慣化すること、基礎から応用へと段階的に進める方法などを知ることが効果的です。さらに、先生や保護者、塾の講師などに相談しながら、自分に合った学習スタイルを見つける努力をしましょう。
②勉強へのモチベーションがないから
勉強の仕方が分からない原因の一つに、勉強へのモチベーションがないことが挙げられます。モチベーションが低いと、学習に取り組む意欲が湧かず、結果として効率的な方法を考えることすら難しくなります。
中学生が勉強にやる気がわかない理由として、目標や目的が曖昧であることが多いです。「なぜ勉強するのか」が明確でないと、学習の意義を見いだせず、ただ「やらされている」と感じてしまいます。また、過去の勉強で成果が出なかった経験があると、「どうせやっても無駄だ」と感じ、さらに意欲を失うこともあります。
この問題を解決するには、まずは小さな目標を設定し、達成感を得ることが大切です。例えば、テストで1つでも正解を増やす、毎日10分だけ復習するなど、達成可能な目標を立てましょう。また、勉強が将来の夢や目標にどのように繋がるのかを考えることも効果的です。さらに、家族や先生からの励ましやサポートを受けることで、自分の努力が評価される喜びを感じ、モチベーションが高まります。
③苦手分野を放置しているから
勉強の仕方が分からない原因として、苦手分野を放置していることが挙げられます。苦手な科目や分野に取り組むのは気が重く、つい後回しにしてしまいがちです。
しかし、その後回しが、基礎的な理解が不足となり、他の内容を学ぶ際につまずく原因となります。特に中学生の学習内容は積み重ねが重要であり、基礎が不十分なまま次の単元に進むと、全体の理解が浅くなり、勉強全般が「分からない」「難しい」という印象に繋がります。また、苦手分野を避け続けることで、自信を失い、勉強への意欲も低下してしまう場合もあります。
この問題を解決するためには、苦手分野を明確にし、少しずつ克服していくことが大切です。例えば、簡単な問題から取り組む、得意な分野と交互に学習する、または先生や友人に具体的なアドバイスを求めるなどの方法があります。さらに、苦手を克服することで得られる達成感は、勉強全体への自信と意欲を高める効果もあります。
④勉強した内容が身になっていないから
勉強の仕方が分からない原因の一つに、勉強した内容が身についていないことが挙げられます。
勉強をしているつもりでも、ただ教科書を眺めたり問題を解くだけでは知識が定着せず、次の日には忘れてしまうことが多いです。
特に、復習を怠ると記憶が薄れやすくなり、学習内容が身に付かないまま次の単元に進んでしまうため、全体的な理解が浅くなります。また、暗記に偏った学習や、問題の解き方を機械的に覚えるだけでは、応用力が育たず、テストや実生活で活用することが難しくなります。
この問題を解決するには、学習した内容を定期的に復習し、理解を深めることが重要です。例えば、授業後にノートを見返す、学んだことを自分の言葉で説明する、問題を解き直して確認するなどの方法が効果的となります。さらに、勉強の際には「なぜそうなるのか」を意識し、単なる暗記ではなく理解を伴う学習を心掛けましょう。
\ 無料相談&進路相談 /
公式ラインを追加
【中学生必見】勉強の仕方が分からない時にやること5選

勉強の仕方が分からない時は、まず目標を明確にすることが大切です。「なぜ勉強するのか」を考え、具体的な目標を設定することでやる気が生まれます。
次に、学校の予習復習の習慣を身に着けましょう。また、自宅学習を習慣化し、問題集を活用することも大事です。
①勉強する目的をはっきりさせる
勉強の仕方が分からない時、まず取り組むべきなのは「勉強する目的をはっきりさせる」ことです。目的が曖昧なままでは、学習に対する意欲が湧かず、計画を立てても継続が難しくなります。例えば、「良い成績を取る」「志望校に合格する」「将来の夢を叶える」など、自分にとって意味のある具体的な目標を設定することが重要です。
これにより、勉強の方向性が明確になり、やるべきことが見えてきます。また、大きな目標を立てたら、それを小さなステップに分けて日々の勉強に落とし込むことが効果的です。例えば、「1日1時間勉強する」「次のテストで5点アップを目指す」など、達成可能な目標を設定することでモチベーションを維持しやすくなります。
さらに、目標を紙に書いて机の前に貼るなど、常に意識できる工夫をすることで、日々の勉強に対する姿勢が変わるでしょう。
②学校の授業の予習と復習をしっかりする
勉強の仕方が分からない時には、まず学校の授業の予習と復習をしっかり行うことが効果的です。予習をすることで、授業内容の全体像を把握でき、どこが分からないのかを事前に確認できます。例えば、教科書を読み、分からない単語やポイントに印をつけておくことで、授業中に集中して聞くべき箇所が明確になります。
一方、復習は学んだ内容を定着させるために欠かせません。授業後24時間以内にノートを見返したり、重要な部分を声に出して確認したりすることで、記憶が長期間保持されやすくなります。また、授業中に解いた問題を再度解き直すことで理解が深まり、応用力も身に付きます。
予習と復習を習慣化することで、学校の授業を効率的に活用でき、勉強の進め方が分からないという悩みも徐々に解消されるでしょう。さらに、予習と復習は、自分の苦手な部分を把握し、苦手を克服するための具体的な勉強方法を見つけるきっかけにもなります。
③学習計画に沿って勉強をする
学習計画を立て、それに沿って勉強を進めることが重要です。計画がないまま勉強を始めると、どの教科にどれだけ時間を使うべきかが分からず、効率が悪くなります。
学習計画を立てる際は、目標を明確にし、それを達成するために必要な具体的な行動をリストアップしましょう。例えば、テストまでに何をどの順番で学習するかを細かく決めることで、無駄な時間を減らし、優先順位を明確にできます。
また、計画は無理のない範囲で設定し、1日の学習時間や取り組む内容を具体的に記載することが大切です。計画に沿って勉強を進めることで、進捗が目に見えるようになり、達成感を得られるため、モチベーションを維持できます。
さらに、計画通りに進まなかった場合は、柔軟に修正しながら取り組むことで、現実的かつ持続可能な学習習慣を身に付けられるでしょう。
④自宅学習を習慣化する
自宅学習の習慣化は成績向上に役立ちます。学校の授業だけでは学びきれない部分や理解が浅い部分を補うためには、家庭での学習が不可欠です。
まず、自宅で勉強する時間を決め、毎日同じ時間に勉強を始めることが習慣化の第一歩です。例えば、放課後や夜の決まった時間に勉強をすることで、自然と勉強のリズムが身につきます。
また、勉強場所を整えることも重要です。集中できる環境を整え、テレビやスマートフォンなどの誘惑を避けることで、効率よく勉強に取り組むことができます。
さらに、毎日の学習内容を少しずつ増やしていくこともポイントです。最初は短時間でも、徐々に学習時間を増やし、復習を取り入れながら進めることで、理解が深まります。毎日の積み重ねが、最終的に大きな成果を生むことを実感できるでしょう。
⑤問題集を活用する
自宅学習の習慣化や、各教科の理解を深めるためには、問題集の活用が非常に役立ちます。
問題集は、教科書で学んだ内容を実践的に理解するための重要なツールです。まず、問題集を使うことで、知識を定着させるだけでなく、問題を解く過程で自分の理解度を確認できます。特に、問題を解いた後に解説をしっかり読んで、間違えた部分や理解が不十分な部分を再確認することが大切です。
これにより、同じ間違いを繰り返さずに学びを深めることができます。また、問題集は繰り返し解くことで効果が高まります。1度解いただけでは十分な定着は望めません。復習を重ねることで、記憶が強化され、次第にスムーズに解けるようになります。
さらに、問題集には様々なレベルや種類があるため、自分の理解度に合ったものを選び、無理なく進めることがポイントです。
勉強の仕方が分からない時の勉強法を教科別に紹介!
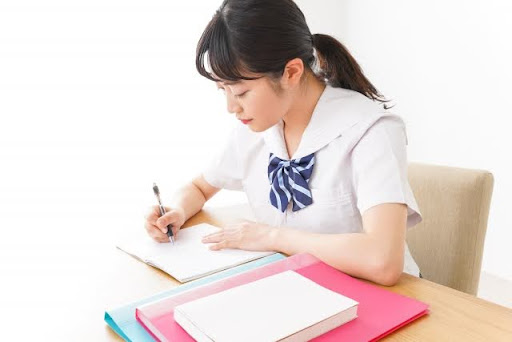
勉強するときは、5教科それぞれに合った勉強法を取り入れましょう。いずれの教科も、計画的に学習し、復習を怠らないことがポイントです。
国語
国語を勉強するにあたっては、まず文章をしっかり読み、内容を理解することが大切です。読解力を高めるために、文章を何度も読み返し、要点を整理して自分の言葉でまとめる練習をしましょう。
また、漢字や語彙力を強化するためには、毎日少しずつ覚えることが効果的です。特に、書き取りや意味の確認を繰り返すことで、記憶に定着しやすくなります。
さらに、文章を書く力を伸ばすためには、日々の作文や日記を通じて、自分の考えを論理的に表現する練習をしましょう。作文の際は、テーマに沿って構成を考え、簡潔で分かりやすい文章を意識することが大切です。
過去問や問題集を活用して、出題傾向を把握し、解答のコツをつかむことも効果的です。特に、文章の要約や意図を答える問題では、文章全体の流れを理解し、重要な部分を見抜く力を養うことが求められます。
英語
英語の勉強は、基礎的な単語や文法をしっかり覚えることから始めましょう。毎日少しずつ単語帳を使って覚え、繰り返し復習することが大切です。
また、文法は理解するだけでなく、実際に使ってみることが重要です。問題集を使って文法問題を解き、間違えた箇所はしっかり復習しましょう。
リスニング力を高めるためには、英語の音声を聞いて、耳を慣らすことが効果的です。音読やシャドウイングを行うことで、発音やリズムにも慣れることができます。
さらに、英作文の練習も大切です。日常的に簡単な文章を英語で書いてみることで、文法の使い方を確認しながら表現力を伸ばせます。英語の勉強では、語彙力や文法の知識を増やすだけでなく、実際に使える力をつけることが目標です。
テスト前には過去問や模擬問題を解き、出題傾向を把握し、苦手な部分を集中的に学習することが効果的です。
数学
数学の勉強は、まず基本的な計算力を身につけることが重要です。計算ミスを減らすために、毎日練習問題を解き、基礎を固めましょう。
次に、教科書の例題をしっかり理解し、類似の問題を自分で解いてみることが大切です。問題を解く際には、解法の手順をしっかり覚え、どのような問題にも対応できるようにします。
さらに、理解が不十分な部分があれば、繰り返し復習して、疑問点を解消しましょう。問題集を使って、基本的な問題から応用問題まで幅広く解くことが効果的です。特に、応用問題では、問題のパターンを見抜き、解法を柔軟に考える力が求められます。
テスト前には予想問題を解き、時間内に解ききる練習をすることが大切です。数学は繰り返し解くことで理解が深まり、問題に対する自信がつきます。苦手な部分は無理に飛ばさず、少しずつ克服していくことが重要となります。
詳しい学習方法はエデュサポブログさんの記事「数学が全くできない中学生必見!原因と苦手克服のための勉強法」が非常にまとまっていて参考となります。
理科
理科を学ぶにあたっては、まず教科書をしっかり読み、重要なポイントを理解することが大切です。理科は概念や公式を覚えるだけでなく、それを実際の問題にどう活用するかが重要となります。
まずは基礎的な内容を理解し、図や表を使って視覚的に整理しましょう。特に、物理や化学の公式や法則は繰り返し使って、実際の問題に適用する練習をしてください。
また、実験や観察の内容をしっかり復習し、理論と実際のつながりを理解することがポイントです。問題集を使って、基本的な問題から応用問題まで幅広く解くことで、理科の理解を深めることができます。特に、計算問題や実験に関する問題では、手順をしっかりと覚え、解答に必要な情報を整理する力を養うのが効果的です。
テスト前には過去問を解き、出題傾向を把握しておきましょう。
社会
社会の勉強では、まず教科書や資料集をしっかり読み、重要なポイントを理解することが大切です。歴史や地理などの内容は、年表や地図を使って視覚的に整理すると覚えやすくなります。特に、歴史の流れや地理の地名・位置関係は、繰り返し確認し、頭の中で整理できるようにしましょう。
また、社会は暗記が多いため、暗記カードやフラッシュカードを使って、効率的に覚えることが効果的です。さらに、過去問や問題集を活用して、実際のテスト形式に慣れましょう。問題を解く際には、解答の根拠をしっかりと確認し、答えを覚えるだけでなく、その背景や理由を理解するようにしてください。特に、時事問題や社会的な出来事についても触れておくと、より深い理解が得られます。
テスト前には、重要な用語や出来事を復習し、要点をまとめておくことが大切です。
勉強の仕方が分からない中学生に親ができること4選

勉強の仕方が分からない中学生に対して親ができることは、まず子どもの現在の学力を把握することです。現在の学力を元に学習方法を見直し、子どもに合った勉強法を見つけましょう。栄養・睡眠の管理も重要です。
①子供の現在の学力を把握する
勉強の仕方が分からない中学生に親ができることで、一番にするべきなのは、子どもの現在の学力を把握することです。まずは、学校の成績やテストの結果を確認し、得意・不得意科目を明確にします。その上で、具体的な学習内容や理解度を親が一緒に確認し、どの部分でつまずいているのかを見極めましょう。これなしに勉強方法は提案できません。塾に相談してもよいと思います。
この情報を元に、子どもに合った学習方法を提案し、サポートしてあげてください。
②子供に合った勉強法を探す
子どもの現在の学力を把握したら、子どもに合った勉強法を探しましょう。学習スタイルは人それぞれ異なります。視覚的に学ぶのが得意な子どもには図や表を使った学習を、聴覚的に学ぶのが得意な子どもには音声教材や説明を活用することが効果的です。
また、短時間で集中できる方法や、休憩を取りながら学習する方法など、子どもが継続できるスタイルを見つける努力をしてください。
③子供の栄養管理をする
子どもの学力を上げるためには、栄養管理をするのも大切となります。勉強に集中するためには、体調が整っていることが重要なためです。バランスの取れた食事を提供し、特に脳に良い栄養素を摂取できるように工夫しましょう。例えば、魚や卵、野菜など、記憶力や集中力を高める食べ物を取り入れることが効果的です。
また、規則正しい食事を心がけ、健康的な生活習慣をサポートしましょう。
④子供の睡眠の管理をする
勉強の記憶が脳に定着するのは睡眠中です。子供の学力を上げるには、睡眠管理も大切となります。十分な睡眠は、学習効率や集中力を高めるために欠かせません。規則正しい睡眠時間を確保し、夜遅くまで勉強させないようにすることが重要です。
また、寝る前のスマホやテレビの使用を避け、リラックスできる環境を整えることが、質の良い睡眠を促進します。
さいたま市の個別指導塾なら芝原塾がおすすめ

中学生が勉強の仕方を学ぶには、試行錯誤して自分にあった勉強法を見つけることが必要です。自分に合う方法を見つけるにあたっては、自分の現在の学力を把握し、苦手分野を見つけることが大切となります。勉強の計画を立てる習慣をつけ、問題集を活用して自宅学習に慣れるようにしましょう。親がサポートできるのは、子供の学力を把握して、合う勉強法を一緒に探してあげることです。
また、子どもが勉強できる体調の維持をするために、栄養や睡眠をしっかり取らせてあげてください。
勉強の仕方を学ぶなら、さいたま市緑区個別指導の「芝原塾」がおすすめです。
一人ひとりの学習状況やペースに合わせた指導を行い、苦手分野の克服や学力向上をサポートしています。また、リーズナブルな料金設定でありながら、つまずきを徹底的に潰していく最大160時間の無料補習や塾長による直接指導を行い、勉強の仕方を丁寧に学ぶことが出来ます。
部活動や習い事との両立も可能な柔軟なスケジュール調整ができるため、忙しい学生にも最適です。
詳しくは芝原塾をチェック!
\ 無料相談&進路相談 /
公式ラインを追加



