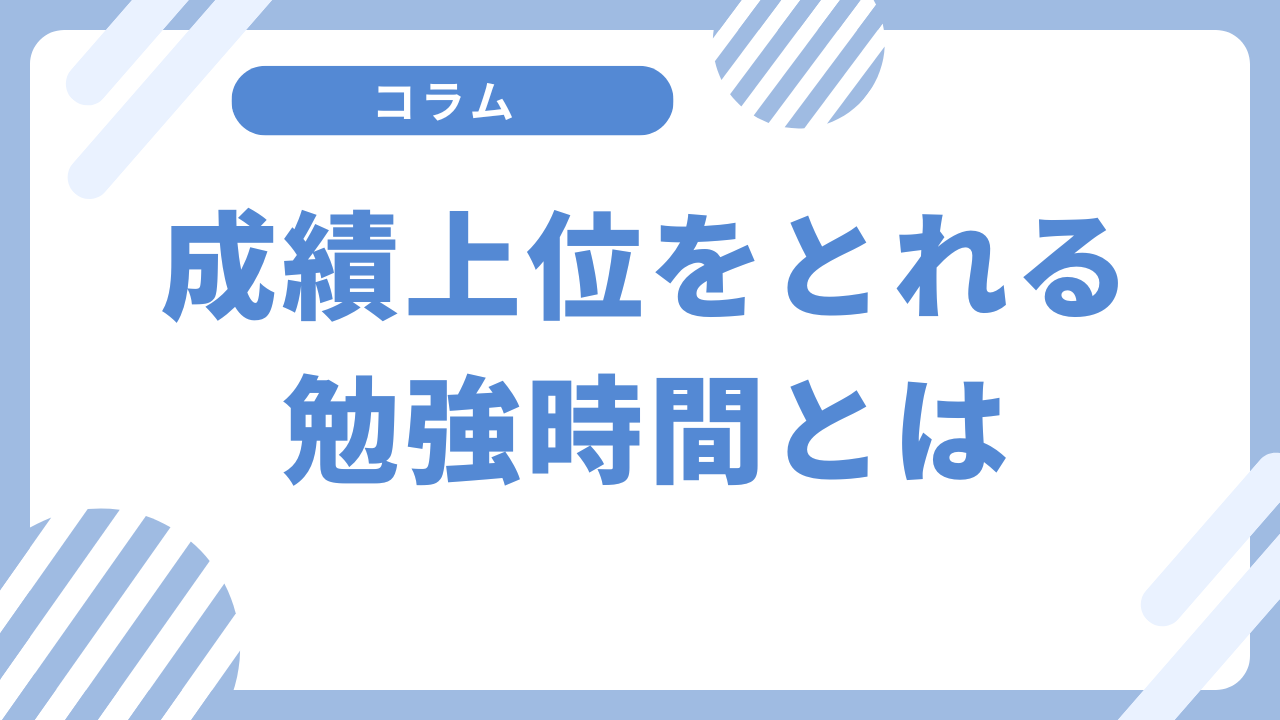
【中学生必見】テストで上位を取れる休日と平日の勉強時間は?スケジュールも詳しく紹介!
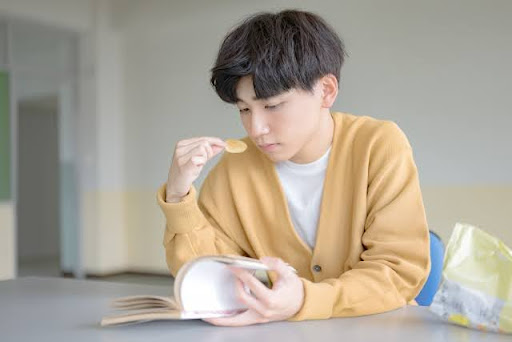
定期テストの点数や順位は、内申点に大きな影響を与えます。そして、この内申点は高校受験を成功させるためにとても重要な役割を果たすため、早い段階からテスト対策を始めることが大切です。
厚生労働省の「21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)」によると、約2万人の児童が学校以外の場所でも勉強をしていることがわかっています。このように、学校以外の場所でも勉強する環境が整っている中で、上位に食い込むためには、家庭学習を上手に活用することが不可欠です。
とはいえ、どれくらい勉強時間を確保すれば良いのかわからないという方も多いかと思います。そこで、この記事では、テストで上位を目指すために必要な勉強時間と、その時間をどうやって確保するかについてわかりやすく解説します。また、効率的な勉強を実現するための一日のスケジュール例もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
\ LINE限定プレゼント /
【中学生必見】テストで上位を取れる平日と休日の勉強時間とは?

まず、テストで高順位・高得点を収めるには、勉強時間をどのくらい、確保すべきなのかをご紹介します。
厚生労働省の「21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)」によると、児童の多くは「1時間未満、30分以上家庭学習をしている」ようです。これは言い換えると、中学生の多くは、普段、1日あたり30分から1時間程度しか家庭学習をしていないということでもあります。しかし、テスト前には勉強時間を増やす子も少なくありません。テスト期間に限り、1日2〜3時間程家庭学習に取り組む子もいるでしょう。
つまり、テストで上位を目指したいという方においては、これ以上の時間、家庭学習を行う必要があるということになります。しかし、具体的にはどのくらいの勉強時間を確保すればいいのでしょうか?ここからは平日と休日で、それぞれ、どの程度、勉強を行うべきなのかを解説していきます。
平日の勉強時間
株式会社DeltaXが行った『塾選調べ:中学生の勉強時間に関する調査』によると、平日に30分から1時間ほど家庭学習をしていると回答した中学生の割合は24%で、これは調査の中で最も多い結果となっています。しかし、テストで高得点を目指すためには、これ以上の家庭学習の時間を確保することが重要です。
具体的には、テスト期間中は1日4~5時間程度の学習時間を目安に、学習を進めることをおすすめします。
休日の勉強時間
同調査においては、休日の勉強時間についても言及されています。最も多かったのは『1時間から1時間半程度家庭学習を行う』中学生で、次に多いのは『2時間から2時間半ほど家庭学習を行う』中学生でした。テストで高順位を目指す場合、これらの生徒たちよりも多くの時間、勉強を行う必要があります。
そのため、テスト期間中は休日に8時間程度の学習時間を確保することをおすすめします。長時間の勉強には適度な休憩も必要なので、時間配分を工夫し、集中力を保ちながら進めるようにしましょう。
中学生で上位を取れるテスト勉強の開始時期
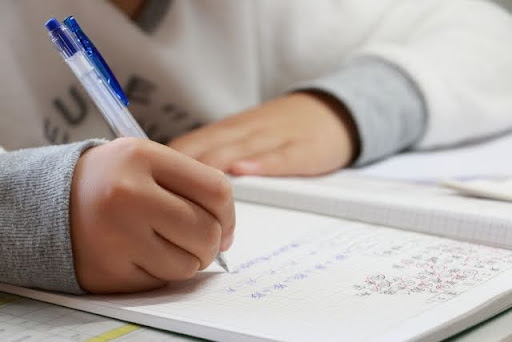
テストで高得点・高順位を狙うには、勉強をいつ始めるかが非常に重要です。
株式会社DeltaXが行った『塾選調べ:中学生の勉強時間に関する調査』によると、中学生の8割以上が『テスト前に勉強時間を増やす』と回答しています。この記事をご覧の方の中にも、テスト期間中に勉強時間を増やしている方も多いのではないでしょうか。
さらに、東京大学社会学研究所とベネッセ教育総合研究所が共同で行った調査では、勉強時間が長い生徒ほど成績が良い傾向があることが示されています。つまり、早めにテスト勉強を始めることで、他の生徒よりも多くの勉強時間を確保できるようになり、結果的に、より良い成績を収められる可能性が高まります。
そのため、定期テストで高成績を目指す方においては、早い段階、具体的にはテストの3週間前から勉強を開始することをおすすめします。早めに準備を始めることで、余裕を持って苦手科目に取り組む時間を確保でき、より効果的に学習を進められるでしょう。
\ 無料相談&進路相談 /
公式ラインを追加
中学生がテストで上位を取るための勉強スケジュールを紹介!

次に、中学生が定期考査で高順位を取るためには、どのようなスケジュールで勉強を進めるべきなのか、具体的なスケジュールの例をご紹介します。
朝型の場合
朝は、1日の中で最も勉強に適していると言われています。というのも、睡眠によって脳に蓄積した疲労がなくなり、脳の機能が向上するからです。
そのため、学習した内容を定着させたい場合や効率的に勉強を進めたい方には、朝起きてすぐに勉強に取り掛かることをおすすめします。
朝に勉強を行うメリットは他にもあります。朝はSNSの通知やテレビなど、集中を妨げる要因が夜に比べて少ないため、より効率的に学習を進めることができます。
このように、朝の時間をうまく活用することで、テスト勉強を効率的に進めることが可能になります。
例えば、8時までに家を出る必要がある場合、6時に起床し、6時半から7時半の1時間を勉強に充ててみてはいかがでしょうか。頭が冴えている朝は、単語の暗記や計算問題といった課題に取り組むのに最適です。
通学中に暗記や、家を出る前に行った勉強の復習を行うのも効果的です。
放課後は、学校で学んだ新しい内容をしっかり復習し、定期考査に向けた問題演習に取り組む時間に使いましょう。特に、その日の授業で理解が浅かった部分や苦手な箇所を重点的に復習することが重要です。数学や理科の演習問題に集中することで、理解が深まります。
夜の時間帯は疲れが出やすいため、軽めの暗記や読書に取り組むのがおすすめです。英単語の確認や定期考査の重要なポイントをノートにまとめるなど、記憶を定着させる作業に使いましょう。
このように、朝の集中力が高い時間を活用し、放課後や夜の時間をバランスよく使うことで、定期考査に向けた効率的な学習スケジュールを組むことができます。無理をせず、規則正しい生活リズムを保つことが、継続的に勉強を進めるためのポイントです。
夜型の場合
しかし中には、朝に勉強時間を確保するのが難しいという方もいるでしょう。そのような方においては、放課後や夜にまとめて勉強時間を確保するようにしましょう。
夜型の人においては、放課後の時間を有効に使い、効率よく学習を進めることが大切です。例えば、帰宅後すぐには、その日の授業内容の復習や宿題に取り組む時間を設けてみてはいかがでしょうか。教科書やノートを読み返し、問題演習を行うことで、理解を深めることができます。
夕食後から就寝までの時間は、定期考査に向けた本格的な学習時間として活用しましょう。苦手な科目にじっくり取り組む、暗記科目を集中して覚えるなど、目標に合わせた勉強を進めることが大切です。この時間帯は脳が活発に働くため、難しい問題や応用問題に挑戦するのにも適しています。
寝る前の時間には、暗記科目や軽めの復習に取り組むのがおすすめです。英単語や歴史の年号など、記憶を定着させる学習を行うことで、翌日の勉強がスムーズに進みます。
ただし、夜遅くまで勉強を続けると集中力が低下しやすいため、適度に休憩を挟むことが重要です。ストレッチや軽い散歩でリフレッシュし、集中力を取り戻しましょう。また、勉強が終わったら、就寝前にリラックスする時間を設け、心身をしっかり休めて翌日に備えることを忘れないようにしましょう。規則正しい睡眠を取ることで、翌日の学習効率が向上します。
夜型の学習スケジュールを組む際は、放課後の時間を無駄にせず、計画的に進めることがポイントです。夜遅くまで勉強する場合でも、しっかりと睡眠を確保することで、バランスを保ちながら効率的に学習を進めることができます。
中学生が上位を取るためにはどうやって勉強時間を作る?

しかし中には、どのように勉強を進めればいいのかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。
実際、ベネッセの『子どもの生活と学びに関する親子調査2023』によると、『上手な勉強のしかたがわからない』と回答した中学生は、全体の6割近くにのぼっていました。
そこで、ここからは『勉強を効率的に進めるためのポイント』及び『勉強時間を確保するためのポイント』をいくつかご紹介します。
①机がいる勉強といらない勉強に分ける
まず、勉強を『机が必要な勉強』と『机が不要な勉強』に分けましょう。
例えば、ノートのまとめ直しや演習問題の解き直しは、机がなければできない『机が必要な勉強』です。
一方で、単語の暗記や復習は、通学中やリビングなど、机がなくても進められる『机が不要な勉強』です。
テスト期間中は机に向かえる時間が限られています。このような状況下で効率的に学習を進めるには、どこでどの勉強をするかを判別することが欠かせません。
これらの結果をもとに、適切な場所で適切な勉強を行うことで、無駄な時間を減らし、学習効果を最大化することができるでしょう。
②短時間でできる内容に勉強を切り分ける
目標を整理し、細分化することも同様に重要です。
例えば『問題集を解く』というタスクは曖昧で、どこから手をつけていいかわからなくなってしまうかもしれません。しかし、問題集の章や問題数を具体的に把握し、それに基づいてタスクを細かく分けることで、取り組みやすくなります。
このように、タスクを具体化するメリットは他にもあります。
例えば、1日に10ページ進める、1週間で20問解くといったように、実現可能で具体的な目標を立てることで、モチベーションを保持して、テスト勉強に取り組むことができます。このような目標設定には、タスクの全体像を把握することが必要不可欠です。
タスクを細分化し、段階的に目標をクリアしていくことで、達成感が得られ、勉強が計画的かつ効率的に進むようになります。
③隙間時間で上手く勉強する
勉強時間を少しでも多く確保するためには、隙間時間の活用が欠かせません。
隙間時間とは、予定と予定の間に生じる短い空き時間のことで、この時間に、先述した『机が不要な勉強』に取り組むことで、時間を無駄なく使えるだけでなく、テスト勉強により多くの時間を費やすことが可能になります。
前述の通り、勉強時間が長い子どものほど、高い成績を収められる傾向にあります。したがって、高い成績を目指すのであれば、隙間時間をうまく活用して、勉強時間を増やすことを強くお勧めします。
④睡眠時間はしっかりと確保する
中には、睡眠時間を削ってまで勉強時間を確保しようとしたり、実際に睡眠時間を減らして勉強している方もいるかもしれません。しかし、睡眠を削ることで得た努力が実を結ぶことは非常に稀です。というのも、睡眠不足が続くと脳に以下のような悪影響が現れることがわかっています。
●脳の前頭葉がダメージを受け、意欲や集中力が低下する
●脳の疲労が蓄積され、記憶力や思考力、判断力が低下する
●脳のシナプスや神経細胞の働きが低下し、情報処理能力が鈍る
●脳の一部が徐々に萎縮し、認知機能が著しく損なわれる可能性がある
これらはすべて、テストで良い成績を収めるために欠かせない能力です。十分な睡眠を取ることで、勉強の効率も格段に上がり、テストで良い結果を出すための準備が整います。そのため、テスト期間においても、十分な睡眠時間を確保するようにしましょう。
【中学生必見】上位を取るための勉強のポイント7選
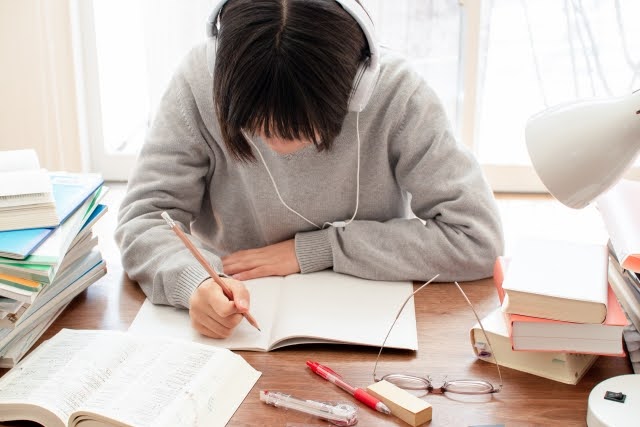
次に、高順位を取るためのポイントを7つ、ご紹介します。これらのポイントを抑えることで、より良い成績を収められる可能性が高まります。
①具体的に目標を決める
まず重要なのは、目標を定め、これを明文化することです。
具体的には、目標を紙に書いて、いつでも目に入る場所に貼るようにしましょう。
例えば、皆さんにおいても、漫画やドラマで登場人物が目標を書いた紙を壁に張り出すシーンを見たことがあるかもしれませんが、これは、目標を意識に刷り込むことを目的としています。
また、目標を定期的に読み上げることも効果的です。声に出すことで耳からも情報が入り、目標が脳に一層定着しやすくなります。
目標はただ頭の中で漠然と考えるだけでなく、視覚や聴覚を通じて外部からの情報として取り入れることで、モチベーションを高め、それを維持することができます。このプロセスを通じて、目標意識と、その達成に向けたモチベーションをしっかりと育てましょう。
②定期テストまでの勉強時間とすべきことを把握する
次に、テストまでにどれくらいの時間があるのか、そしてその間に何をしなければならないのかを改めて確認してみましょう。自分が1日にどれくらいの時間を勉強に充てられるのかを見直すことも重要です。
これによって、必要な勉強量と限られた時間をどのように使うべきかが明確になり、スケジュールを立てる上で欠かせない要素を把握できます。
例えば、定期テストの2週間前から勉強を始めると仮定し、部活のテスト休みが1週間前から始まる場合を考えてみましょう。
最初の1週間は部活があるため、食事や入浴時間を除いて勉強時間は21時から1〜2時間程度しか確保できません。しかし、部活がテスト休みに入る1週間前からは、夕方に1時間、21時から1〜2時間の勉強時間を確保できるようになります。
休日は部活がないため、1日8時間程度の勉強が可能です。
これを合計すると、2週間で最大57時間の勉強時間を確保できることになります。これを5教科で割ると、1教科あたり約11.4時間が割り当てられます。つまり、各教科に約11時間を充てることになります。
仮にテスト範囲が30ページだとした場合、1時間で約2.7ページを進めなければなりません。しかし、進めるだけではなく、定期テストで確実に正解するためには、知識の定着が非常に重要です。そのため、問題集を3周するなど、繰り返し学習することが必要となります。これを頭の中で考えるのではなく紙に書きだしてください。書き方がわからないという場合は東大毎日塾さんの勉強計画表がプレゼントされているので活用されましょう。期間限定のようなのでお早めに。
このように、限られた時間を最大限に活用するためには、何をどれだけ進めるべきかを考えながら、効率的にテスト勉強を進める方法を見つけ出すことが重要です。
③実現可能な勉強スケジュールを立てる
次に、先ほどの計画をもとに、実際のスケジュールを立てていきましょう。スケジュールを作成する際に大切なのは、予備日や休憩時間をしっかり確保することです。
中には「予備日や休憩時間を設けるのは甘えではないか?」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、予備日は急な体調不良や予期しない出来事に対応するために必要不可欠なほか、休憩は、勉強のモチベーションを維持するために非常に重要な役割を担っています。
例えば、皆さんは「ポモドーロ・テクニック」という時間管理法をご存知ですか?これは、1980年代にイタリア人のフランチェスコ・シリロが考案した方法で、25分の作業時間と5分間の短い休憩を繰り返すことで、集中力を持続させるという方法で、この方法は、様々な場所で取り入れられており、効率的な学習や仕事をサポートしています。
つまり、適度な休憩を取ることで、集中力を持続できるだけではなく、脳の疲労を軽減して、長時間の勉強にも耐えることができます。これを踏まえて、スケジュールには休憩時間をしっかり盛り込み、予備日も入れるようにしましょう。
④学校から配られた問題集やプリントに取り組む
学校から配られた問題集やプリントにも必ず取り組むようにしましょう。
ほとんどの場合、定期テストの設問は、学校の先生によって作成されます。そのため、学校から配布された教材に出てくる内容がテストに多く出題される傾向があります。つまり、市販の問題集を解くよりも、学校から配布された問題集やプリントに取り組んだ方が、テスト対策としては格段に効果的です。
学校の教材は、テストで求められる内容をしっかりと反映しているため、これに集中して学習することで、テストに直結した実力を養うことができます。自分の理解度を確認しながら進め、わからない部分や不安な箇所は繰り返し復習することが、効率的で確実な勉強法と言えるでしょう。
⑤学校の授業に集中する
中には、授業中にテスト勉強をする、いわゆる「内職」をしている人もいらっしゃるかもしれません。しかし、そのような方に、お伝えしたいのは、普段の授業にこそ、テストを制するためのヒントがあるということです。
前述のように、定期テストは通っている学校の先生が作成しています。実際、先生は授業中に「ここが大事」「テストに出るかもしれない」「この公式は覚えておこう」などのヒントを口にしていることがよくあります。これらはテストに直結する重要な情報であり、しっかりと授業に集中して聞いておくことが、テスト対策として非常に効果的です。
授業をただ受けるのではなく、先生が伝えたいポイントに意識を向け、理解を深めながら進めることが、成績アップへの近道です。
⑥休憩を上手に挟む
また、前述の通り、集中力を持続させるためには、適度な休憩を挟むことが非常に重要です。長時間勉強を続けると、どうしても疲れが蓄積してしまい、作業効率や生産性が低下してしまいます。そのため、勉強の合間に休憩を入れることで、集中力をリフレッシュさせ、効率よく学習を進めることができます。
休憩を取り入れることで、脳がリセットされ、次の勉強に対しても新たな気持ちで臨むことができます。勉強時間が長くなればなるほど、適切な休憩は効果を発揮します。無理に長時間続けるよりも、休憩を挟みながら勉強する方が、最終的に得られる成果は大きくなります。
そのため、より良い成績を収めたいという方においては、休憩を挟みつつ、勉強に取り組むことをおすすめします。
⑦得意・不得意教科の勉強時間の割合
限られた時間を効率よく活用するためには、得意な科目と不得意な科目を交互に学習することが効果的です。やる気が出ないからといって得意科目だけをやっていても、不得意科目は伸びませんし、逆に不得意科目に長時間集中しても時間が足りなくなってしまいます。
得意科目と不得意科目を交互に学ぶことで、脳が自然に切り替わり、集中力が維持しやすくなります。「勉強が進んでいる」と実感することで、やる気がアップし、学習効率も向上します。短時間で切り替えを行うことで、集中力を高め、より効率的に学習を進めることができます。
まとめ

当記事では、定期考査において、高得点・高順位を収める方法について解説しました。効果的な勉強法として、計画的な学習時間の確保、得意科目と不得意科目を交互に学習すること、そして早期の勉強開始の重要性を挙げました。これらの方法を実践することで、限られた時間を有効に使い、効率的に知識を定着させることが可能です。
成功の鍵は「継続的な努力」と「自分に合った学習スタイルの確立」にあります。自分のペースで着実に勉強を進め、テスト前に余裕を持って取り組むことで、目標達成への道が開けます。あなたの努力が成果に繋がるよう、ぜひ実践してみてください。
中学生の休日の勉強時間を有効活用するには、質の高い学習環境が欠かせません。芝原塾では、一人ひとりに合わせた個別指導を通じて、効率的に学力を伸ばすサポートを行っています。特に、学年をさかのぼり、苦手分野を徹底的に解消し、自信を持って次の学年へ進む準備ができる、最大160時間の無料補習が魅力的。
さらに、部活動や習い事などのスケジュールに柔軟に対応しており、休日でも学びを止めない体制が整っています。運動と両立しながら成績アップを目指したい方に最適です。休日の勉強時間を最大限に活かしたいなら、ぜひ芝原塾で新しい学びの一歩を踏み出してみませんか?
詳しくは芝原塾公式サイトをご覧ください!
\ 無料相談&進路相談 /
公式ラインを追加



