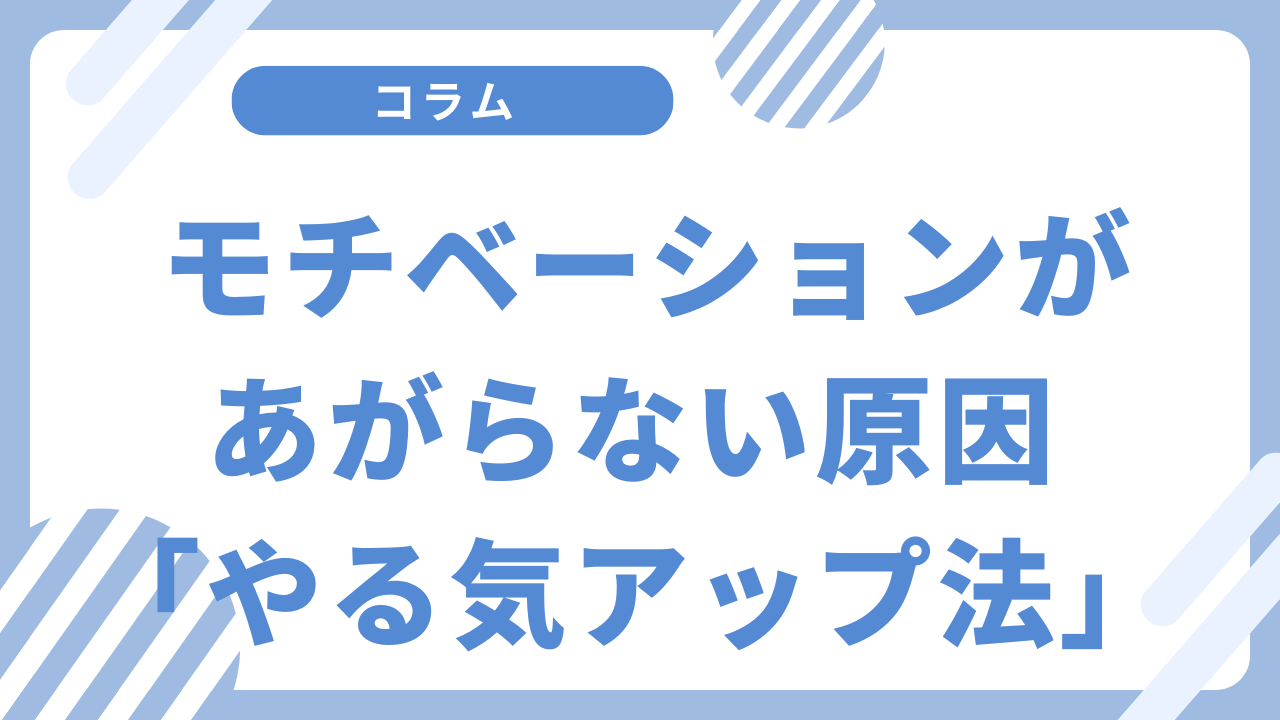
高校受験のモチベーションが上がらない原因とは?やる気がアップする方法を徹底解説!

「頑張らなきゃ」と思っているのに、なぜかやる気が出ないのは、実は誰にでも起こりうることです。
でも安心してください。その原因を知り、正しい方法で対策すれば、やる気は自然と湧いてきます。
この記事では、中学生が高校受験をする際に今からできる「やる気アップ」の方法をわかりやすく解説します。高校受験に向けて、一緒に一歩ずつ進んでいきましょう!
\ LINE限定プレゼント /
高校受験のモチベーションが上がらない5つの原因とは?

高校受験のモチベーションが上がらない原因は、大きく5つに分けられます。それぞれの原因を理解することで、効果的な対策を立てることができます。
①勉強自体が嫌いだから
学習指導の現場では、勉強が嫌いな生徒の多くが、どこでつまずいているのかを自分で把握できていないことがよく見受けられます。「勉強が嫌い」と一括りにするのではなく、まずどの教科が特に苦手なのか、そしてその教科のどの単元からわからなくなったのかを具体的に確認していきましょう。さらに、どんな問題でつまずくことが多いのか、なぜその部分がわからないと感じるのかまで、段階を追って分析してみることが大切です。
たとえば、英語が苦手な場合、「文法全般」ではなく「関係代名詞の使い方」など、具体的な単元レベルまで分解してみましょう。このように細分化することで、克服すべきポイントが明確になり、一つずつ解決していくことができます。
②受験勉強をする意味がわからないから
受験勉強の意味が見出せないのは、将来の目標や志望校が明確になっていないことが主な原因です。目標を持って学習に取り組む生徒は、学習への取り組み方に大きな違いが見られます。目標があることで、日々の学習に意味を見出しやすくなり、より多くの時間を学習に充てる傾向があります。
志望校が決まっていない場合、まずは自分が将来どんな職業に就きたいのか、そのためにはどの高校に進学すべきかを考えることが大切です。将来の夢と進学先を結びつけることで、受験勉強の意味を見出すことができます。
実際に、志望校のオープンキャンパスに参加したり、学校説明会で在校生の話を聞いたりすることで、具体的な目標を見つけられた生徒も多くいます。
③受験勉強のやり方がわからないから
受験勉強のやり方がわからない場合、まず重要なのは学習計画の立て方を理解することです。多くの生徒が「やることが多すぎて何から始めればいいかわからない」と感じています。
効果的な学習計画を立てるには、まず自分が受験勉強に使える「手持ちの時間」を把握することから始めます。次に、入試までに学習すべき教材の総量を確認し、それらを入試までの週数で割ることで、1週間あたりの学習量を決めていきます。このような具体的な計画があれば、「今週はここまで」という明確な目標を立てやすくなります。
④毎日が忙しく勉強に割ける時間が少ないから
部活動や習い事との両立に悩む生徒は少なくありません。しかし、重要なのは「時間がない」と諦めるのではなく、限られた時間を効率的に使うことです。
一般的に、長時間同じ課題に取り組み続けると集中力は徐々に低下していきます。そのため、短い時間で区切って集中的に学習し、適度な休憩を取り入れることで、より効果的に学習を進めることができます。
たとえば、朝30分早く起きて英単語を覚える、通学時間に暗記物に取り組む、夕食後の1時間を確保するなど、すき間時間を活用することで、毎日コンスタントに学習時間を確保することができます。
⑤睡眠不足等で集中力が続かないから
受験生に多い悩みの一つが、集中力が続かないことです。その主な原因は、不規則な生活習慣にあります。特に睡眠不足は、学習効率に大きく影響を与えます。
睡眠不足は単なる疲労だけでなく、記憶力の低下にも直接影響します。十分な睡眠を取ることで、学習した内容が記憶に定着しやすくなり、より効果的な学習を行うことができます。特に、テスト前の徹夜勉強は避け、規則正しい睡眠習慣を心がけることが重要です。
また、偏った食生活や運動不足も集中力低下の原因となります。栄養バランスの取れた食事と適度な運動を心がけることで、学習効率を高めることができます。特に、野菜や果物、たんぱく質をしっかり摂取し、糖分の取りすぎに注意することが重要です。
\ 無料相談&進路相談 /
公式ラインを追加
高校受験へのモチベーションを上げる6つの方法

モチベーションが上がらない原因が分かったところで、具体的な対策方法を見ていきましょう。以下の6つの方法は、多くの受験生が実践して効果を実感している方法です。
①目標を決める
受験勉強を継続的に行うためには、具体的な目標設定が重要です。「なんとなく勉強する」のではなく、「第一志望校に合格する」という明確な目標があることで、モチベーションを保ちやすくなります。
目標設定の例として、以下のような組み合わせが効果的です。
まず長期目標として「第一志望校合格」や「部活と両立しながら偏差値を5上げる」といった大きな目標を設定します。
次に、その達成のための短期目標として「今週は英単語を50個覚える」「毎日数学の問題を10題解く」などの具体的な目標を立てます。
さらに、日々の学習の指針となる当日目標として「今日は理科の重要公式を3つ覚える」「国語の長文を2題解く」といった、より細かな目標を設定していきましょう。
②勉強した量がひと目でわかるようにする
努力の成果を目に見える形にすることで、モチベーションは大きく向上します。例えば、学習時間や解いた問題数、覚えた英単語の数などを記録してグラフ化すると、自分の成長を実感しやすくなります。
具体的な方法として、カレンダーに学習時間を記入する、スマートフォンのアプリで学習記録をつける、壁に貼った模試の成績表で自分の成長を確認するなど、自分に合った記録の取り方を見つけることが大切です。
学習記録をつけることで、自分の進歩を目に見える形で確認することができます。日々の努力の積み重ねが視覚的に分かることで、「頑張っているな」「少しずつ前に進んでいるな」と実感でき、継続的な学習へのモチベーションにつながります。
③集中できる学習環境にする
学習環境は、モチベーションに大きな影響を与えます。自宅で勉強する場合は、スマートフォンを別室に置く、机の上を整理する、適度な明るさを確保するなど、集中できる環境作りを心がけましょう。
しかし、自宅学習だけでは集中力が続かない、やる気が出ないという生徒も少なくありません。そんな時は、図書館や学習塾などの学習に特化した環境を活用することをおすすめします。
特に個別指導の学習塾では、生徒一人ひとりの学習ペースに合わせた環境が整っています。例えば、さいたま市緑区にある芝原塾では、生徒一人ひとりの学力に応じた「無学年方式」で基礎から丁寧に指導し、「できる」までしっかりとサポートする環境を整えています。実際に、一桁だった成績が80点以上に上がるなど、着実な成果を上げている生徒も多くいます。
④勉強を頑張ったご褒美を用意する
適度な報酬は、モチベーション維持に効果的です。例えば、「今日の目標を達成できたら好きな動画を15分見る」「一週間計画通り勉強できたら欲しかった本を買う」といった具合に、自分へのご褒美を設定してみましょう。
ただし、ご褒美が勉強時間を圧迫しないよう、適度な範囲に収めることが重要です。小さな目標達成には小さなご褒美、大きな目標達成には少し大きめのご褒美を設定するなど、メリハリをつけることをおすすめします。
⑤一緒に頑張れる仲間を作る
受験勉強を乗り切るには、同じ目標を持つ仲間の存在が大きな力となります。学校の友達や塾の仲間と定期的に学習状況を共有したり、お互いの進捗を確認し合ったりすることで、モチベーションを高め合うことができます。同じ志望校を目指す仲間と交流することで、孤独感を感じることなく学習を継続できます。
⑥高校の学校説明会に行ってみる
志望校の学校説明会への参加は、受験勉強のモチベーションを大きく高める機会となります。実際の校舎や設備を見学し、在校生の話を聞くことで、自分が目指す学校生活をより具体的にイメージできるようになります。
高校の学校説明会では、以下の点をしっかり確認しましょう
・授業の雰囲気や教室の設備
・部活動の活動状況
・通学時間や通学経路
・学校の校風や雰囲気
・在校生の様子
また、学校説明会で得られる入試情報や学校の雰囲気は、志望校選びの重要な判断材料となります。できるだけ早い時期から参加することで、モチベーションを高く保ちながら計画的な受験準備を進めることができます。
高校受験のモチベーションを維持する4つの方法

モチベーションを上げることができても、それを長期間維持することは簡単ではありません。しかし、以下の4つの方法を実践することで、入試本番まで安定したモチベーションを保つことができます。
①実現可能な学習計画を立てる
モチベーションを維持するには、達成可能な学習計画を立てることが重要です。やる気に任せて「1日10時間勉強する」といった無理な計画を立てると、続かずに挫折してしまう可能性が高くなります。
効果的な学習計画を立てるには、まず自分の生活リズムを把握することから始めましょう。部活動や習い事、家族との時間なども考慮に入れ、無理なく継続できる学習時間を設定します。現実的な目標設定ができている生徒は、日々の学習を無理なく継続できる傾向にあります。達成できない目標を立てるよりも、少しずつでも着実に実行できる計画を立てることが、学習の継続につながります。
②勉強を毎日の生活の中で習慣化させる
毎日同じ時間に同じ場所で勉強することで、自然と学習が習慣化されていきます。
例えば、朝の通学時間を使って英単語を覚え、放課後は部活前の30分で数学の問題を解くといった具合に、日常生活の中に学習を組み込んでいきましょう。さらに、夕食後は必ず机に向かって宿題をこなし、お風呂上がりには社会の年号を確認、就寝前にはその日の学習内容を10分程度で振り返るなど、生活リズムの中に学習を定着させることが効果的です。
新しい習慣を身につけるには、継続的な取り組みが必要です。最初の数週間は特に大変ですが、この時期を乗り切ることができれば、その後は少しずつ習慣として定着していきやすくなります。無理のない範囲で始めて、徐々に学習時間を増やしていく方法がおすすめです。
③細かく休憩を挟みながら勉強する
集中力を維持するには、適切な休憩を取ることが大切です。一般的に人間の集中力は40分程度で低下すると言われており、それ以上続けても効率は下がる一方です。そのため、40分勉強したら5〜10分の休憩を取る「ポモドーロ・テクニック」などの時間管理法を取り入れることをおすすめします。
ただし、休憩時間にSNSを見たりゲームをしたりすると、勉強に戻りにくくなってしまいます。休憩中は軽い体操やストレッチ、水分補給など、リフレッシュできる活動を選びましょう。これにより、次の学習でも高い集中力を維持することができます。
④模試の結果を気にしすぎない
模試の結果は確かに重要な指標ですが、一回一回の結果にとらわれすぎるのは逆効果です。模試で予想以上に良い点数が取れたからといって油断したり、悪い点数だったからと落ち込みすぎたりせず、あくまでも現在の実力を確認するための指標として捉えることが大切です。
むしろ、模試で見つかった弱点を克服するチャンスというふうに考えてください。多くの受験生が経験していることですが、模試の結果に一喜一憂するのではなく、「次はここを改善しよう」という前向きな姿勢で臨むことで、着実な成長につながっていきます。
高校受験のモチベーションを下げてしまう保護者の行動とは?

子どものモチベーションを上げようと思って取った行動が、逆効果になってしまうことがあります。以下の4つは、特に注意が必要な行動です。
子供が勉強していないことを叱る
「なぜ勉強しないの!」「このままじゃ志望校に行けないわよ!」といった叱責は、子どもの学習意欲を低下させてしまいます。叱責は学習に対する興味や意欲を減少させ、特に生徒の自己肯定感を、学習意欲の低下につながるとされています。
叱ることで一時的に勉強に向かわせることはできても、それは恐怖や不安からくる行動であり、持続的なモチベーションにはつながりません。むしろ、長期的には生徒の学習意欲を向上させる効果は期待できず、勉強に対する負のイメージを植え付けてしまう可能性が高くなります。
勉強していない子どもに対してペナルティを与える
「勉強しないならゲームを取り上げる」「部活を辞めさせる」といったペナルティは、子どもの反発心を強めるだけです。こうした強制的な手段は、表面的には行動を変えることができても、長期的には生徒の学習意欲を低下させ、逆効果になることが指摘されています。
ペナルティを与えられることで、子どもは勉強を「やらされている」と感じ、内発的な学習意欲が失われてしまいます。また、好きな活動を制限されることで、ストレスが溜まり、さらに勉強から遠ざかってしまう悪循環に陥りやすくなります。
兄弟や同級生と比較する
「お姉ちゃんはもっと頑張っていたのに」「隣の○○君は毎日3時間勉強しているのよ」といった比較の言葉は、子どものプライドを深く傷つけます。他人との比較は、劣等感や嫉妬心を生み出し、学習意欲を著しく低下させる要因となります。
比較されることで、子どもは自己肯定感を失い、「どうせ自分には無理」という諦めの気持ちを抱きやすくなります。その結果、受験勉強に対するモチベーションが下がってしまいます。
勉強に対する過剰な介入をする
「もっとこうすべき」「この方法じゃダメ」と、細かく指示を出したり、学習方法を強制したりすることは、子どもの自主性を奪ってしまいます。過剰な介入は、子どもの学習意欲を低下させる大きな要因の一つです。
中学生という時期は、自己主張が強くなり、親からの過度な干渉を嫌う傾向があります。学習方法や時間の使い方など、ある程度は子ども自身に任せ、見守る姿勢を持つことが重要です。
高校受験のモチベーションを上げるために保護者ができることとは?

これまで見てきた対策に加えて、保護者の適切なサポートは子どものモチベーション向上に大きな影響を与えます。以下の3つの行動を意識することで、子どもの学習意欲を効果的に引き出すことができます。
まずは子供の話を聞く
とある研究によると、保護者が子どもの話をしっかりと聞く時間を持つことで、子どもは自己肯定感を高め、それが学習意欲の向上につながるとされています。特に、親が子どもの話を傾聴することで、子どもは自分の気持ちを理解されていると感じ、学習に対する前向きな姿勢が育まれていくことが示されています。
子供の小さな変化や成長に気づき褒める
日々の小さな進歩や努力を見逃さず、具体的に褒めることが重要です。「最近、机に向かう時間が増えたね」「英単語を覚える工夫をしているんだね」など、子どもの変化に気づいていることを伝えましょう。変化を認められることで、子どもは自信を持ち、さらなる努力への意欲が湧いてきます。
ポジティブな言葉をかける
子どもが前向きに勉強に取り組めるよう、励ましの声かけを心がけるようにしてください。例えば、模試の結果が思わしくなかった場合でも、「できなかった部分が明確になって良かったね」「次はもっと良い結果が出せそうだね」など、やる気が出る言葉で励ますことで、子どもは困難を乗り越えるエネルギーを得ることができます。
高校受験を意識し始めたら芝原塾に相談!

高校受験のモチベーションを上げ、維持していくためには、受験生自身の取り組みと保護者の適切なサポートの両方が重要です。この記事のポイントは以下の3つです
1. モチベーション低下の原因を特定して対策を立てる
2. 具体的な目標設定と環境づくりで意欲を高める
3. 保護者は子どもの気持ちに寄り添って支援する
受験勉強は長期戦です。一時的なやる気ではなく、継続的なモチベーションを保つことが合格への近道となります。
もし学習環境や勉強方法にお悩みでしたら、さいたま市緑区の芝原塾の個別カウンセリングをご利用ください。生徒一人ひとりに合わせた学習プランと、モチベーションを保つためのサポート体制を整えていますので、お気軽にご相談ください。
\ 無料相談&進路相談 /
公式ラインを追加



